- 共働き・共育てで毎日忙しくて時間に余裕がない!
- 時間がない中でも、子どもへの教育が気になる…
- 「STEAM教育」というのを聞いたことがあるけど、簡単にできるのかな?
ふと気がつくと、ショート動画やゴシップニュースをながめて時間をつぶしてしまっていることはないでしょうか。
病院や役所での順番待ち、習い事の送り迎えなど、共働き夫婦の生活にはさまざまな「スキマ時間」が潜んでいます。
もしその時間をぼんやり過ごしているのなら、もったいないです。
「スキマ時間」を子どもの興味や好奇心をかき立てる学びのチャンスに変えることができます。
そのカギとなるのが、STEAM教育を取り入れたスマホのミニゲームです。
ほんのちょっとした工夫で、子どもの思考力や創造力をグングン伸ばすことができます。
この記事で紹介する内容を参考にして、「スキマ時間」を子どもの「マナビ時間」にチェンジしましょう!
STEAM教育とは、科学(Science)、技術(Technology)、工学(Engineering)、芸術/リベラルアーツ(Art /Arts)、数学(Mathematics)の頭文字を取った造語です。
それぞれの分野を超えて学ぶことで、問題の発見・解決力を育てる教育です。
変化の激しいこれからの時代を切り拓く未来の教育として、現在注目を集めています。
スキマ時間で始めるSTEAM教育の価値

あまり意識していなくても、日常のあちこちに「スキマ時間」が生まれる瞬間があります。
ほんの数分を有効に活用してみるだけで、子どもにとっては色々なの学びが得られるかもしれません。
ここでは、スマホのミニゲームからSTEAMを体験する際の大切なポイントを見ていきましょう。
スキマ時間は宝物!親子の時間を創造的に活用するコツ

数分の待ち時間をただ何もせずに過ごすか、「マナビ時間」にするかは、考え方次第です。
大人にとっては「今日の夜ご飯、何にしようかな…」と考える程度の時間でも、子どもにとってはワクワクの瞬間になることがあります。
たとえば、親子でパズルゲームを遊んでいるときに「どこに置けばいいかな」「少し回したらハマるかな」などと話しているうちに、自然と頭を使う練習になっています。
こうした「スキマ時間」の小さな積み重ねが、子どもの学びを大きく広げるきっかけにつながります。
子どもが「できた!」と嬉しそうに笑う姿を見ると、大人も思わず笑顔になっちゃいますよね。
楽しいだけじゃない!STEAMの重要性
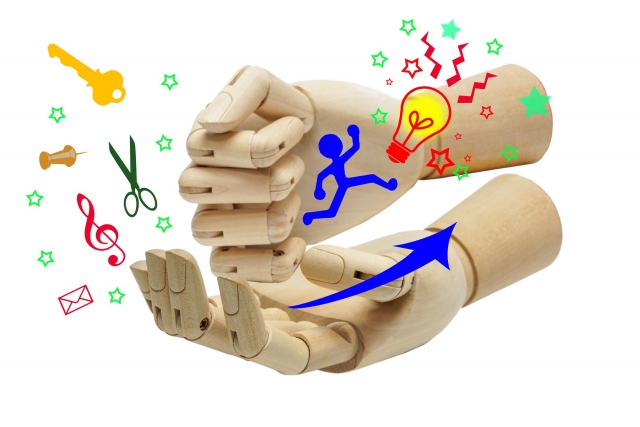
STEAMとは、Science(科学)、Technology(技術)、Engineering(工学)、Arts(芸術/リベラルアーツ)、Mathematics(数学)をまとめた言葉です。
少し難しそうに感じるかもしれませんが、これらの分野には未来につながる学びの要素がたくさん詰まっています。
たとえば、大人が「このゲームで数式を使うなんて難しそう…」と尻込みしてしまっても、子どもは「なんか面白そう!」と意外に興味を持つことがあるかもしれません。
ゲームを遊んでいるうちに、「こんな解き方があるんだ!」と発見できるのがSTEAM教育の面白いところです。
ゲーム感覚で始められるので、初心者でもとっつきやすいというメリットがあります。
親子のやりとりこそ学習効果を高めるカギ

「ここがわからない!」「ヒントちょうだい!」と子どもに言われたときは、絶好のサポートチャンス!
- この形と似ているのはどれかな?
- ここを押すと何かかわるかもしれないね
- そのボタンを押してみる勇気はある?
あれこれ指示を出すのではなく、ほんの少しの声かけをしてみてください。
うまくできたときには、「すごい、天才っ!」と大げさに褒めてあげると、満足感100%の笑顔が返ってくるでしょう。
こうした親子のコミュニケーションを楽しめると、子どもはもっと学びに意欲を持つようになります。
ゲームでも、どうやって問題を解決しようかと考えるうちに、子どもの視野がぐんっと広がっていきます。
 まさと
まさと娘がうまくできたときに「さすが!毎日保育園に行って頑張ってるもんね!」と褒めると、満足感と照れ臭さが相まった表情を浮かべていました
大人でも「頑張ってる」って言われたら嬉しいですよね
STEAMアプリが思考力と創造力を高めるわけ
なぜ、「スキマ時間」で遊ぶミニゲームが子どもの思考力や想像力を伸ばすことにつながるのでしょうか。
ここからは、STEAM系ミニゲームだからこそ得られる効果について解説します。
五感と知的好奇心を刺激するインタラクティブ体験


スマホゲームは、色彩豊かな映像や音声といった要素が組み合わさり、指先の操作に合わせて画面の中の世界が次々に変化する点が特徴です。
子どもにとっては「触ったら世界が動いた!」という不思議な感覚につながります。
たとえば、実験系のアプリでは「粉と液体を混ぜてみたら色が変わった!」という驚きを体験できたりします。
こうした、教科書だけでは体感することが難しい五感への刺激が、子どもの探究心を大きく育てるのです。
もっと試してみたい、ほかの材料ではどうなるのだろう、といった知的好奇心こそが学びの原点といえます。
試行錯誤を促すゲーム設計が思考力を後押し


多くのSTEAM系ミニゲームでは、失敗しても「もう一度チャレンジ」程度で気軽にリトライできます。
パズルや謎解き系のゲームでは、間違えた分だけ「次はこうしてみよう」と考える回数が増えるため、結果的に子どもの思考力を鍛えてくれます。
「ここを動かしたら壊れちゃったから、あっちに移してみよう」など、試行錯誤の末に正解にたどり着いたときの喜びは格別です。
成功すると素直に喜び、失敗してもすぐにまた取り組もうとするこのプロセスこそが、考える力を高めるエネルギーになっています。
大人はちょっとしたヒントを出しながら、子どもの自主性を見守ってあげるとよいでしょう。



娘の横で見ていると、ヒントや答えを言いたくなってムズムズします
「我慢、我慢…」と自分に言い聞かせて、子ども自身の力で解かせるようにしています
子どもの興味と学習内容を結びつける柔軟性


その子によって、好きなものや興味のある分野はさまざまです。
「電車しか興味がない」「かわいい動物じゃなきゃイヤだ」など、好みがはっきりしている子も多いかもしれません。
STEAM対応のアプリにはプログラミング要素があるものや、アートを楽しめるもの、算数や図形の学習に役立つものなど、多種多様なゲームがあります。
さらに、短時間でクリアできるステージが多いという点も、共働き家庭にとっては大きなメリットです。
「なんか面白そう!」と子どもが思ったものから始めさせると、勉強のような意識が少なくスムーズに学びを楽しむことができるでしょう。
続けるうちに「もっと知りたい!」と感じるようになれば、より深い学習へと進めるきっかけになるかもしれません。
おすすめのSTEAMミニゲームアプリ一覧


実際にどのようなアプリがあるのか、短い時間で遊べてSTEAM学習の入り口にもなるミニゲームを3つご紹介します。
子どもの好みや家庭の方針にあわせて検討してみてください。
パズル&図形認識系アプリ


四角や丸、三角のパーツを組み合わせて図形を作るアプリは、初めて触れる子どもでもわかりやすいところが魅力です。
正解の位置にパーツがはまったときの「ピタッ」という感覚が気持ちよく、子どもをグッと引きつけます。
難易度が上がると「むずかしいー!」とむしゃくしゃするかもしれませんが、その分クリアしたときの達成感は大きいです。
音や色がにぎやかなものは小さな子でも操作しやすく、立体のパズル系なら空間認識力を高める効果も期待できます。
プログラミング思考を育むロジック系アプリ


「前に進む」「右へ曲がる」「もし壁に当たったら戻る」といった命令ブロックを組み合わせてキャラクターをゴールまで誘導するタイプのゲームは、プログラミング的な思考を養うのにぴったりです。
最初は難しそうに見えても、キャラクターがかわいい場合が多く、子どもは意外と抵抗なくチャレンジしてくれます。
ステージをひとつクリアするたびに「やった!」という達成感を味わえるため、モチベーションが持続しやすいのもポイントです。
大人が「次はどんな命令をすればいいと思う?」と子どもに問いかけることで、ゲームを通じた対話が生まれます。
学校の勉強とはまた違った角度で楽しめるのが魅力です。
サイエンス&実験系アプリ
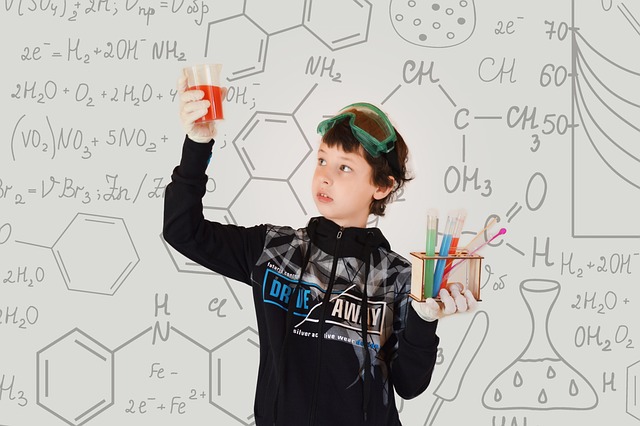
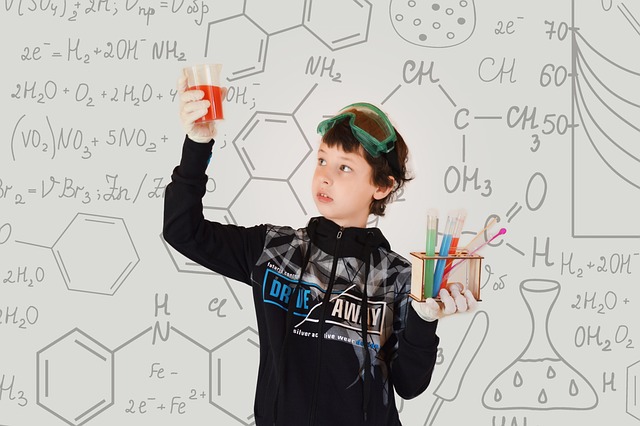
「薬品を混ぜたら爆発しちゃった…!」というような体験ができるのは、デジタルならではの醍醐味といえます。
現実では準備や安全面のハードルが高い実験でも、アプリの中なら気軽に何度でも試すことができます。
植物を育てるシミュレーション系のアプリも人気があり、「水を与えすぎると根腐れを起こす」「日光が足りないと成長しない」といった現実の自然環境に近い設定が取り入れられています。
ミニゲームを遊んだあと、実際の植物を見たときに「さっきのゲームと同じだね」と気づくこともあり、学びがぐっと深まるはずです。
親子で未来を広げるスキマ学習


ここまで、「スキマ時間」を活用してSTEAM学習を導入するメリットや、具体的なアプリの例をご紹介してきました。
最後に、これらのポイントをもう一度整理します。
1日の中で学びの芽を見逃さない
朝の準備が終わって家を出るまでの数分や、習い事が始まるまでの待ち時間など、「ちょっと遊んでみちゃう?」と誘えるタイミングは意外にたくさんあります。
短時間で楽しめるゲームなら、ダラダラと長引かずに集中して取り組めるので、忙しい共働き家庭にもぴったりです。
「時間がないからこそ集中できる」という場合もあるので、子どもの興味を引くようなゲームを用意しておくとよいでしょう。
こうした短い時間の積み重ねが、子どもの「自分で学んでいる」という自信にもつながり、思わぬ成長を見せてくれるかもしれません。



私たち共働き家庭はまとまった時間がとれません
たった数分の使い方が大切になってきます
遊びと学びを両立させる親の声かけ
子どもの集中力が切れかけているときは、「面白い?」と尋ねたり、「どうして上手くいかなかったのかな?」と声をかけたりするだけで、考えを深めるきっかけになります。
褒めるときは「すごい!」だけよりも
- ここの工夫がすごいね!
- よく思いついたね!お母さんは気付かなかったな〜
- これに気づいちゃうなんて、さすが!
などと具体的に伝えると、子どものやる気がさらにアップ!
大人がわざと「大変、助けてー!」とおどけると、子どもの方が「ここを直せばいいんだよ」と得意げにアドバイスをくれることもあります。
こうしたやりとりを積み重ねるうちに、親子の絆や子どもの学習意欲がいっそう強まります。
「やり過ぎ」を防ぐルールづくりも大切
夢中になりすぎると、ついつい時間を忘れてしまうのがゲームの良さでもあり、怖さでもあります。
長時間のプレイは姿勢の乱れや視力の低下、生活リズムの崩れなどを招くおそれがあるため、家族であらかじめルールを決めておくことが大切です。
- ゲームは一回15分まで
- タイマーが鳴ったらそこでおしまい
- 一回につき1ステージまで
などの約束をしておくと、子どもも守りやすいです。
もし「まだやりたい!」と言われたら、「続きはまた次の休憩のときにしよう」と伝え、健康を保ちながら学習を継続できるように心がけましょう。
ルールを設けることで集中度が増し、ゲームをクリアしたときの満足感も高まります。
親子での学びが未来につながる
幼いころに「こんなことできるんだ!」と強く感じた体験は、将来大きな可能性を生み出す種になります。
サイエンス系の実験アプリで「化学反応」に興味を持った子どもは、理科の授業を楽しめるかもしれません。プログラミングが好きになった子は、ものづくりやロボットに関心を持ち続けるかもしれません。
そんな小さなきっかけが、大人になってから「実はあのときのゲーム体験が夢の始まりだったんだよね」という思い出になる可能性も十分にあります。
何気ない「スキマ時間」に仕込んだ学びが、子どもの未来を大きく広げることにつながるのは、とても素敵なことですよね。
ここまで、「スキマ時間」を活用したSTEAM教育の魅力をご紹介してきました。
共働きで忙しい日々の中でも、少し視点を変えてスマホのミニゲームを取り入れてみるだけで、子どもは多くの新しい知識や感動を得られます。
まずは気軽にミニゲームを試してみて、「面白い!」「もっとやってみたい!」という気持ちを引き出してみてください。
そうしたポジティブな体験を通して、「スキマ時間」を子どもの「マナビ時間」にチェンジしましょう!
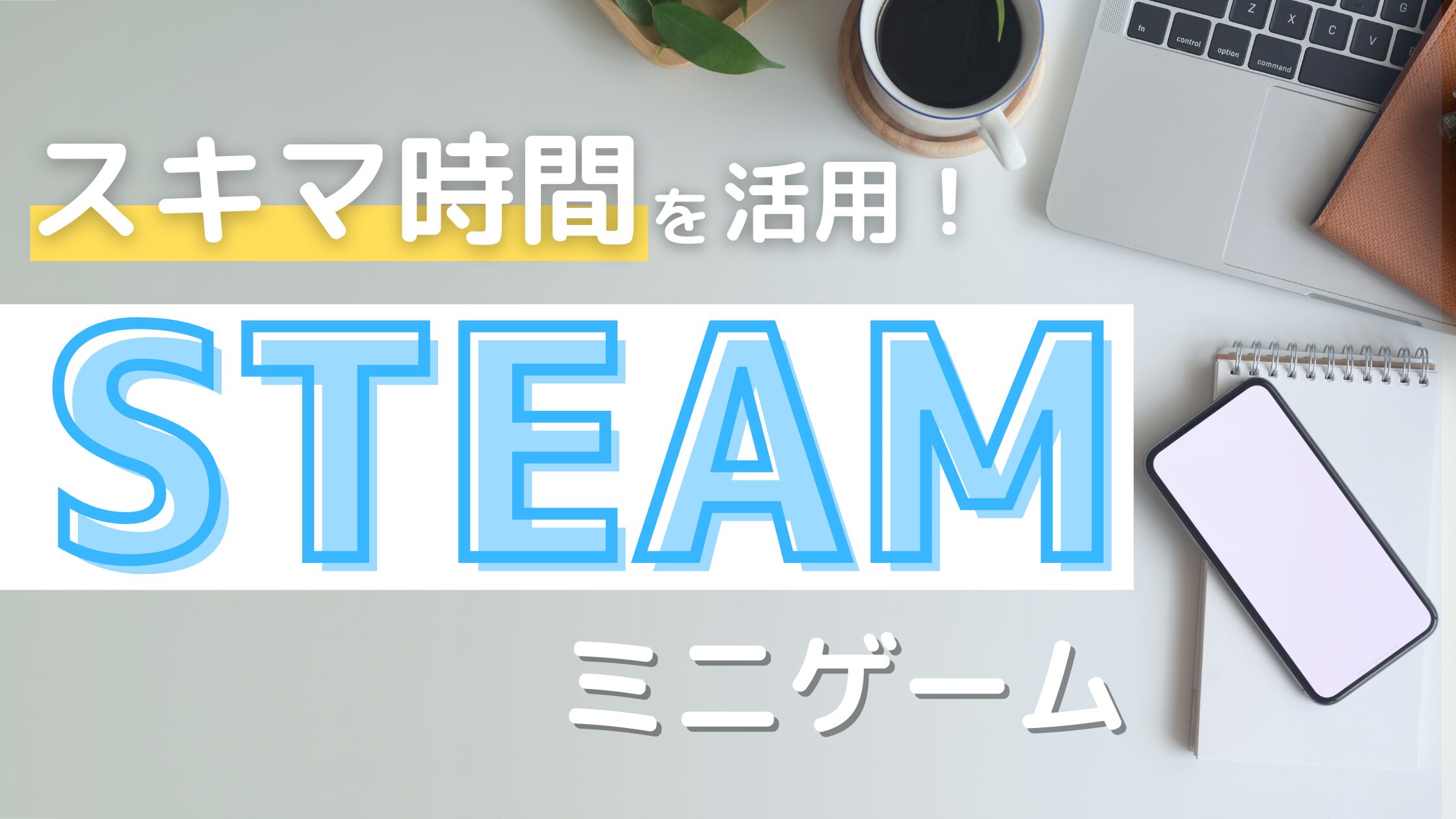
コメント